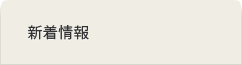|
平素より当社商品をご使用いただき、誠にありがとうございます。 シャッターを"安全"かつ"安心"してお使いいただくためには、取扱説明書に沿った正しい"お取り扱い"と、日頃からの"維持・管理"が大切です。取扱説明書に記載されている注意事項をお読みいただいた上で操作し、お客様ご自身によるお手入れや日常点検とあわせて、当社サービスマンによる保守点検を行っていただきますようお願いいたします。 特に設置してから年数が経過したシャッターをご使用されている場合は、部品が摩耗していたり、安全装置が未装着の場合もありますので、"日常点検"と"保守点検"をぜひ実施していただくとともに、安全装置を設置していただきますようお願いいたします。 |
| 1.シャッターのお取り扱いについて |
|
シャッターをご使用する際は、次の"ご使用上の注意事項"に従って操作してください。また、商品毎の取扱説明書・表示ラベルをよくご確認の上、正しくご使用いただきますようお願いいたします。 シャッターを正しくご使用いただかない場合、思わぬ事故につながる場合がありますのでご注意ください。 |
|
<ご使用上の注意事項
> |
||
| ○ |
シャッターの下に人がいないこと、 物がないことを確認してから 操作してください。 |
|
| ○ |
シャッターの下に物を置いたり、 車を停車させないでください。 |
|
| ○ |
シャッターの開閉中は、 人や車の出入りはしないでください。 また、顔や手を出したり シャッターの下に物を置いたり しないでください。 |
|
| ○ |
シャッターの動作中はそばを離れず、 シャッターが停止するまで目を 離さないようにしてください。 |
|
| ○ |
台風などの強風時には、 シャッターに近づいたり動かしたり しないでください。 また、中柱つきの商品では 中柱を確実に固定してください。 |
|
| ○ |
シャッターの点検・修理には専門知識が必要です。お客様による修理・分解・改造は絶対にしないでください。 |
|
| ○ |
製品を長期間にわたって安全かつ安心してご使用いただくためには日常点検と定期点検が必要です。 |
|
| ○ |
シャッターの操作・動作について少しでも不確かな点がありましたら、取扱説明書でご確認いただくか、当社メンテサービスセンターまたは最寄りの営業所にお問い合わせいただき、確認の上でご使用ください。 |
|
| ○ |
いつもと異なる動きをしたり異音がするときは速やかに使用を中止して、以下の処置を実施した上で、当社メンテサービスセンターまたは最寄りの営業所へご連絡してください。 |
|
|
異常音や異常振動がある。 |
上限、下限の正しい位置で停止しない。 |
|
|
異常時の処置
|
| 2.日常点検のお願い |
| 日常点検として、お客様ご自身で以下の事項を実施していただきますようお願いいたします。 |
| ○ |
表示ラベルの脱落、破れ、はがれなどがないか確認してください。読めなかったり、正しく貼られていなかったり、破損していた場合は、新しいラベルと交換するために、当社メンテサービスセンターまたは最寄りの営業所へご連絡してください。 |
|
| ○ | 開閉状態を確認してください。 | |
|
||
| ○ |
日常点検で異常を感じたり、以下のような症状を確認された場合は、速やかに使用を中止し、当社メンテサービスセンターまたは最寄りの営業所へご連絡してください。 症例
|
|
異常時の処置
|
||
| 3.重要な確認のお願い | |
| (1) | 『危害防止装置』の蓄電池について |
|
『危害防止装置』は、防火シャッター(防火防煙シャッター)に設置が義務づけられており、非常時にシャッターが閉鎖した際、人がシャッターに挟まれても人体に危害を及ぼさないようにするための装置です。この装置は、建築基準法施行令第112条第14項に規定され、人命を守るための重要な役割をもっています。 この『危害防止装置』に使用している連動中継器の 蓄電池の寿命は 約5年 となっています。 いつでも正常に作動するために、 定期的な蓄電池の交換が必要となります。 下記方法で確認していただき、寿命が近づいている場合は、当社メンテサービスセンターまたは最寄りの営業所へご連絡してください。 電池試験スイッチ操作により異常表示ランプ(蓄電池表示ランプ)が点滅すると蓄電池の消耗異常のお知らせです。 |
|
| ●随時閉鎖装置(スイッチボックス) | ●随時閉鎖装置(レール内蔵型) |
|
|
|
| (2) | 水圧開放装置『パニックオープナー』の蓄電池について |
|
『パニックオープナー』は、非常時に外部から消防ホースの水圧を利用し、停電時でも人が通れる高さまでシャッターを開放する装置です。 この装置は、消防法施行規則第5条第2項3号を満たすために設置されており、非常時に避難または消防活動のための重要な役割をもっています。 この『パニックオープナー』に使用している非常電源盤の蓄電池の寿命は、設置場所の温度等で異なりますが、 常温での寿命は 約3年 となっています。 いつでも正常に作動するために 定期的な蓄電池の交換が必要となります。 下記ラベルで確認していただき、寿命が近づいている場合は、当社メンテサービスセンターまたは最寄りの営業所へご連絡してください。 |
|
|
| 4.保守点検のおすすめ | |
|
シャッターは、設置からの経過に伴う経年劣化や、開閉動作に伴う部品の消耗などが生じます。 不調や故障を早期に発見し、最適な使用状態を保ち続けるためには、保守点検が必要です。お客様に行っていただく"日常点検"と、専門技術者による"定期点検"を実施していただくことをおすすめします。 定期点検では商品の状態とともにご使用期間やご使用回数などを考慮して、部品交換やシャッターのお取替えについてもご提案いたします。 また、シャッターが故障した場合には、修理対応のARM(オール・ラウンド・メンテナンス)にご連絡してください。フリーダイヤル0120-49-1080で365日24時間対応いたします。 |
|
| 5.安全装置の設置について |
| ご使用になっているシャッターの種類によって、安全装置が設置されている製品と設置されていない製品があります。 |
| (1) | 防火シャッターには『危害防止装置』の設置が義務づけられています。 | |
| 煙感知器などが感知して作動する防火シャッターの安全装置は、『危害防止装置』と呼ばれ、平成17年12月以降に着工した建物には設置が義務づけられました(建築基準法施行令第112条第14項)。これ以前に設置されたシャッターは、増改築や大規模修繕等が行われない限り法律が適用されないため、平成17年12月より前に建てられた多くの建物には"危害防止装置"が設 置されていません(既存不適格)ので、安全性を確保するために設置していただくことをおすすめします。 | ||
|
|
『危害防止装置』とは、煙若しくは熱感知器、または手動閉鎖装置の作動により防火シャッターが自重で降下している際に、シャッターが人や物に接触すると閉鎖動作を停止し、人や物がなくなると再び降下を始めて完全に閉鎖し防火区画を形成する装置です。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 火災発生時、煙感知器または熱感知器からの信号によるシャッターが閉鎖します。 | 座板が障害物に接触し、感知スイッチが作動するとシャッターが停止します。 | 障害物がなくなると約10秒後にシャッターが閉鎖します。 | シャッターは全閉し、停止します。 |
| (2) | 一般の管理用シャッターには『障害物感知装置』の設置をおすすめします。 |
| 日常的に出入り口等で使用されている管理用シャッターの安全装置は、『障害物感知装置』と呼ばれ、平成7年7月に施行されたPL法(製造物責任法)以降、安全確保のため製品への設置を進めてきました。 |
|
|
|
|
|
|
|
① シャッターが降下 |
|
②障害物に接触 |
|
③シャッターは停止、 反転上昇して停止 |
|
|
『障害物感知装置』とは、シャッターの降下中に障害物を感知すると停止または反転し、万一のトラブルを未然に防止する装置で、光電感知方式、ボトム感知方式、負荷感知方式などがあります。 |
|
| 近年施工されたシャッターには『障害物感知装置』が設置されていますが、過去に設置され、長年にわたってご使用いただいているシャッターには『障害物感知装置』が設置されていない場合があります。『障害物感知装置』は、既にご使用いただいているシャッターにも設置することができますので、ご使用中のシャッターに『障害物感知装置』が設置されていない場合には、安全確保のため、当社メンテサービスセンターまたは最寄りの営業所へお問い合わせの上、設置していただくことをおすすめします。 | ||
|
【連絡先】 フリーダイヤル 0120-49-1080 ◇フリーダイヤルは携帯電話からはご利用になれません。 または、 最寄りの営業所 
当社加盟団体 社団法人日本シヤッター・ドア協会発行 ①「シャッターをより安全にお使いいただくために」 へ ②「製品の経年劣化による事故事例」へ ③「電動シャッターによる重大事故について」へ |
||